
鉄道模型の最安値を探す!

おすすめの鉄道模型動画
この動画では、DD51形による重連運転は非効率のため、貨物専用機であるDF200形牽引による寝台特急北斗星を組成しました。実際にはこのような運転事例はありませんでした。全くのフィクションですがご了承ください。
DF200形ディーゼル機関車は、JR貨物が1992年(平成4年)から製作した電気式ディーゼル機関車です。
幹線における電化区間の割合が低い北海道においては、無煙化以降の貨物輸送は電化・非電化区間の区別なくDD51形を主力としてきました。JR移行後の輸送量増大や貨物列車の高速化に対し、DD51形の出力不足で恒常的に重連での運用を要したことに加え、北海道の厳しい気候風土による車両の老朽化も顕在化してきました。これを受け、重連運転の解消と老朽車両の置換えを目的として開発されたのが本形式です。
公募により”ECO-POWER RED BEAR”(エコパワーレッドベア)という愛称がつけられ、車体側面にロゴが描かれました。なお、JR貨物が設計・開発したディーゼル機関車で愛称がつけられたのは本形式のみとなっています。
1994年鉄道友の会ローレル賞(第34回)を受賞しました。
車体は前面を<の形に傾斜させた20 m級の箱型です。重連運転は想定されず、正面に貫通扉はありません。屋根高さを車両限界いっぱいの4 mにして機器類の艤装空間を確保しています。側面より見て車体中央部に放熱器・冷却ファンなどの冷却系統、その両隣に動力源となる機関と発電機のセットを搭載し、主変換装置・補助電源装置など電気系統機器は運転台の真後ろに各々配置されています。機器配置はおおむね前後対称となっています。運転室の前後方向の寸法が小さく、乗務員扉は側面向かって左側のものは車体中央付近に設けられ、右側のものは運転室に設ける点対称の配置となりました。JR貨物所属車の外部塗色は濃・淡グレーと朱色の組み合わせです。
動力伝達方式は従来の主流であった液体式ではなく、国鉄DF50形以来の電気式(ディーゼル・エレクトリック方式)として設計されました。これは増大した出力に対応する大容量液体変速機の研究・開発が国鉄DE50形の試作を最後に中止されて久しいことと、VVVFインバータ制御など、長足の進歩を遂げた電気機器を採用することで、駆動系の小型化と保守の軽減が図れるためでした。
主機関として、ツインターボ・インタークーラー付きV型12気筒ディーゼル機関を2基搭載しています。これは、同じくV型12気筒ディーゼル機関を搭載する国鉄DD51形と比べてエンジン排気量が61.1 Lから46.3 Lへとダウンサイジングされ小型高出力化が図られており(排気量あたりの出力はDML61Zのおよそ2.2倍になる)、これにより、エンジン・発電機・主変換装置・主電動機を含めたパワーユニットの小型化に貢献しました。初期の車両はドイツ・MTU社製12V396形(定格出力1,700 PS / 1,800 rpm)が採用されましたが、50番台以降はJR貨物・JR九州所属車ともコマツ製SDA12V170-1形(定格出力 1,800 PS / 1,800 rpm、最大出力 2,071 PS / 2,100 rpm)に変更されました。これはDD51のB更新工事車に搭載されている、同社製SA12V170-1(1,100 PS / 1,500 rpm)のアフタークーラをデュアルサーキット化したものです。発電機は各エンジンにつき1つずつ、計2基搭載されており、全車が東芝製FDM301形、自己通風冷却回転界磁式ブラシレス同期発電機(定格出力1550 kVA/1,800 rpm)となっています。
車体長を詰めながら表面積を稼ぐため、1エンジンあたり2枚の冷却器を前後視でV字形に配置し、上方に設けられたファン1基とで一つのモジュールを形作るようになっており、それを2組搭載しています。冷却ファンの駆動は従来の静油圧式を止めて電動式とし、モジュール全体を容量の大きな箱状としたことでDD51のシュラウドと比べて通気抵抗も低減しました。
主回路電機品、補助電源装置、モニタリングシステムなど電機品は、すべて東芝製です。
主電動機はかご形三相誘導電動機FMT100形(320 kW)を6基搭載しています。1個のインバータで1個の主電動機を制御する1C1M方式の個別制御システムにより、定格の動輪周出力はDD51形の1.5倍となり、平坦線で110 km/h以上の均衡速度(800 t牽引時)を維持することができます。6軸駆動となったことで、起動時の粘着安定性も向上しました。主電動機の装架方式は国鉄・JRの電気機関車で汎用的に用いられる「吊り掛け式」で、動軸への動力伝達は主電動機回転子軸の小歯車と車軸側の大歯車の係合による1段歯車減速方式です。2群の機関・発電機を有することで、片機関故障時も主回路繋ぎ換えにより6軸駆動を保ち、速度は低下するものの登り勾配での起動力を維持することができるようになっています。
機関車本体用の単独ブレーキ(単弁)は電気指令式空気ブレーキを採用しています。被牽引車両への編成ブレーキ(自弁)には自動空気ブレーキを採用しています。また、自車が牽引される場合は牽引する機関車からの空気圧指令によりブレーキが作動する仕組みになっています。発電ブレーキは30 km/h以上で作動するようになっており、その時には発電ブレーキのみでブレーキを掛けますが、編成ブレーキ力が不足と判断された場合には、機関車の空気ブレーキがフォローする仕組みとなっています。台車は枕ばねにダイヤフラム式の空気ばねを用いた軸梁式のボルスタレス台車のFDT100形(両端)FDT101形(中間)で、牽引力の伝達はZリンク方式です。基礎ブレーキ装置は片押し式踏面ブレーキで、ブレーキシリンダ・ブレーキテコと一体化して台車に装架するユニットブレーキとなっています。軸重を抑えるため軽量化された本形式の台車構造は、後続の新形式機関車にも基本として用いられています。
耐寒・耐雪構造としては運転室では気密対策、暖房能力を向上させ前面窓ガラスは熱線入り、温風式デフロスタを装備。台車では砂マキ管の目詰り防止のため、電動機の排気熱による温風ヒーターを装備。ブレーキ装置では、車輪踏面と制輪子間に雪が噛込むのを防ぐために耐雪ブレーキ制御を行います。ブレーキ制御装置と除湿装置には保温ヒーターを装備しました。
ATSはATS-SFを装備していますが、北海道でのATS-DNの装備が進んだことから、0番台の大半はATS-SFの機能を持ちながらもATS-DNと互換性のあるATS-DFに変更されています。この工事は2016年6月までに完了しました。
本形式の50番台は、1999年12月から2004年1月にかけ、13両(51 – 63)が製造されました。
駆動用機関をコマツ製のSDA12V170-1形に変更しました。これはDD51形のB更新工事施工車に搭載されたものと同系統で、部品の共通化による保守性向上を主目的としています。車体構造の変更はありませんが、製作途中で”RED BEAR”の愛称が決定し、車体に愛称のロゴが描かれました(既存機にも順次施工)。スカートは灰色、JRFロゴは白色です。
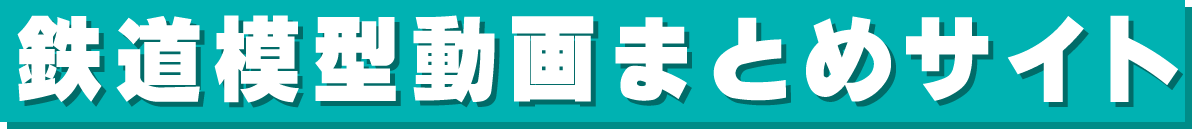
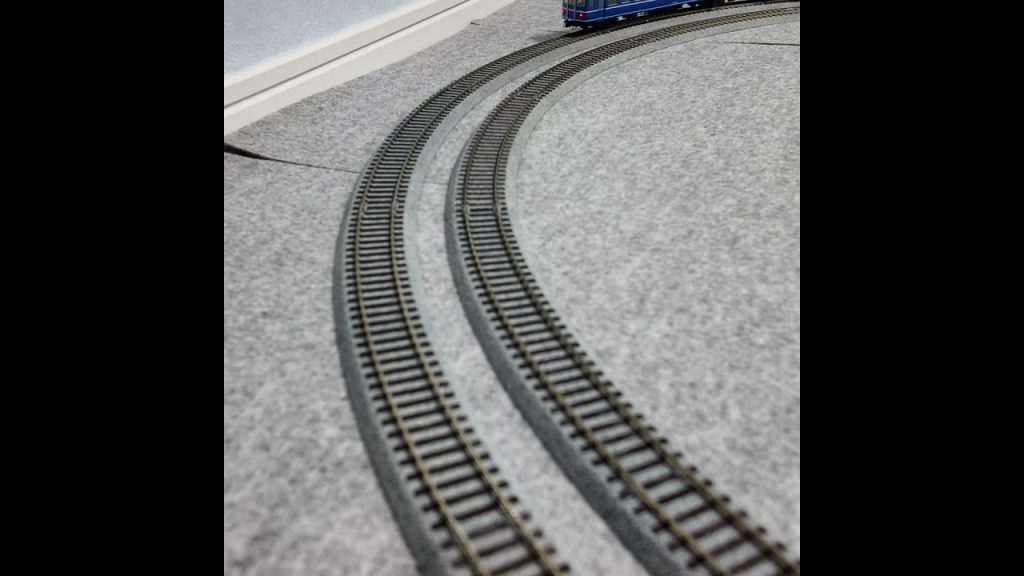
![[高架線離合‼︎] E257系5500番台同士(JR特急 草津⇆上野) 高架線カーブ走行シーン‼︎ #nゲージ #jr東日本 #e257系 #高崎線 #特急 #吾妻線 #kato #離合 #鉄道模型](http://tetsumo-info.com/wp-content/uploads/2025/04/E2575500JR-n-jr-e257-kato--1024x576.jpg)
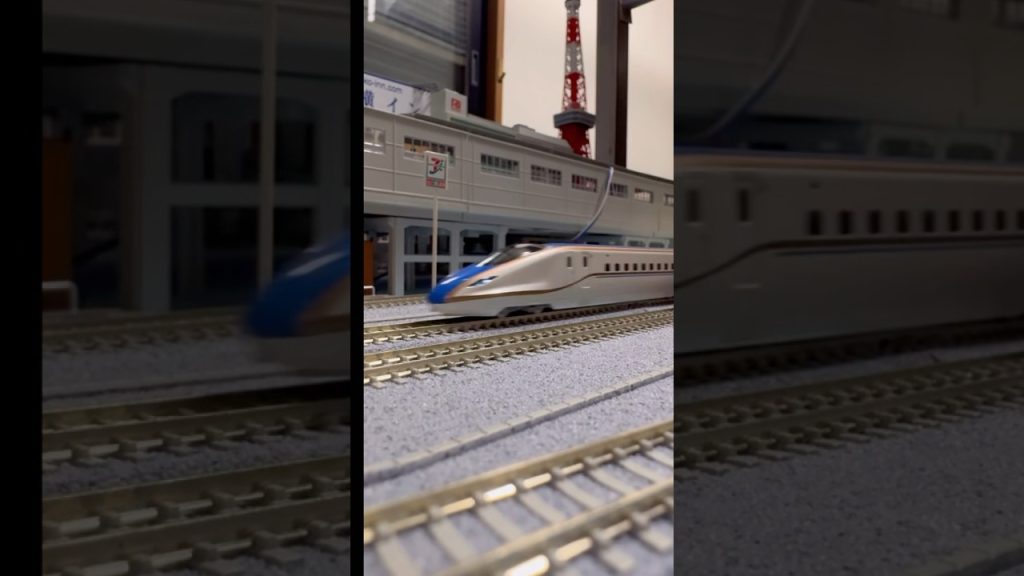


![Nゲージ[鉄道模型]KATO E2系あさま E7系かがやき](http://tetsumo-info.com/wp-content/uploads/2025/01/NKATO-E2E7-1024x576.jpg)